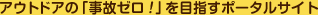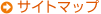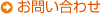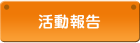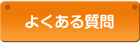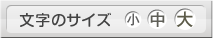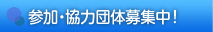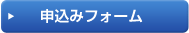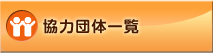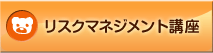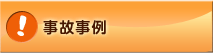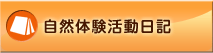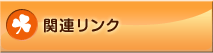注意喚起~落雷事故防止対策について
4月10日に奈良市にある学校のグラウンドに雷が落ち、部活動をしていた生徒6人が病院に搬送された事故がありました。
「ピカッ」と光った後から音が鳴るまでの秒数を数えて、雷が近いかどうかを推測したりしていないでしょうか?この方法は昔のやり方で、今は、研究が進み、遠い近いに関係なく、「ピカッ!ゴロッ!」つまり音が聞こえたり光が見えたりした場合は、すぐに活動を中断し、避難するのが鉄則です。
平成8年、大阪・高槻市で行われたサッカーの試合中に高知市の高校のサッカー部員だった男性が、落雷を受け、目や足などに重い障害が残る事故がありました。事故がおこった後では取り返しがつきません。防げる事故だけはどうにか防いでいきましょう。
4月10日の事故を受けて、日本サッカー協会が、4月18日【JFAより注意喚起】熱中症対策および落雷事故防止対策について
を公式HPで発表しています。
日本サッカー協会では、過去の落雷事故を受けて、協会参加で活動するすべての活動体に対してガイドラインへの順守を求めています。
自然体験活動をする中では、周辺施設なども必ずしも緊急時に安全性が確保されている環境にないケースが多いと思います。
運営団体には、雷やゲリラ雷雨など天候の急変時にどのようにするかも含めた準備と安全性の確保が求められます。
①活動の前には、天気予報を確認し、活動中も観天望気も含めて、専門的な天気予報サイトなどを活用して注意を怠らない事。
②荒天になり予兆があった場合は、躊躇なく活動を中止・中断すること。
③安全な避難場所は、閉め切ることの可能な鉄筋などの建物の中
④感覚に頼らず、必ず天気予報サイトなどで雷雲の状況などを確認します。
最後の雷から何もない状態が30分以上経過してから再開します。
雷から身を守るには(気象庁)
【参考】
天気予報サイトについては、様々なサイトがあるので、その情報を積極的に把握すること。
ナウキャスト(気象庁)では、「雷注意報」の発表状況や「雷ナウキャスト」で実際にどこで 落雷・雷発生が高まる予測になっているのか情報収集ができます。
※山や海など活動場所により専門のサイトもあるので、必要に応じて調べて活用しましょう。
※川では、その場の天候に問題が無くても上流部で大雨があったりして増水するおそれがあります。流域の天気にも注意しましょう。
【活動の再開について】
・天候が好転しても、安易に活動を再開せず、同じくサイトなどを使って状況をチェックしてから再開しましょう。
【雷に打たれる事故が発生してしまった場合】
・2次災害の可能性がありますから、傷病者への対応には十分注意してください。
・万が一、人が雷に打たれてしまったら、救急車を要請します。
・被害者の体が電気を帯びたままになっていることはありませんから、まずは通常の応急救護と同じように、意識や呼吸の確認をします。異常がある場合は、心停止応急対応として、胸部圧迫をおこないAEDを使用します。
迅速に避難を行い落雷事故の被害に遭わないようにするためには、現場に居合わせている全員が、「音が聞こえたり光が見えたりした場合は、すぐに活動を中断し、避難すること」を共通認識として持つことが重要であり、速やかに行動に移せる体制をとっておくことが必要です。
避難を指示する役割は、責任者だけが担うのではなくそこにいる全員です。全員が落雷の兆候に目を向けるようにし、気づいた人が声を掛け合い速やかにその情報を共有するようにして避難しましょう。
【主催者の方へ】
活動を始める前に「雷注意報」が出ている時には、活動の変更や中止も視野に入れ、実際にどこで落雷や雷の発生が高まるかの情報を収集しましょう。そして、事前に危険が予測される場合には、危険を回避するための行動を関係者間であらかじめ共有しておき、躊躇なく安全な場所への避難行動に移れるようにしておきましょう。
今回の落雷事故も平成8年の事故も大きな事故の要因は、避難せずにスポーツを継続していた/避難するタイミングが遅れてしまったことです。
落雷事故を防ぐためにはまず「知る」ことが大切です。過去の事故を踏まえて、判断基準も変化しています。
あなたが「知る」ことも大切ですが、活動現場にいる全員が正しい知識を共有することが重要であることを忘れないでください。